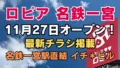2025年 スマホ新法とは?やさしく解説
「スマホ新法」は、正式名称を 「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和6年法律第58号)」 といい、2025年12月18日に全面施行される新しい法律です。
公正取引委員会が監督を担当し、スマホの世界をもっと自由に、安全に、便利に使えるようにすることが目的で、特にアプリの流通や課金ルールに大きな変化をもたらします。
スマホ新法の目的(自由・安全・便利)
これまで、スマホのアプリを入れるときは、ほとんどの場合 AppleのApp Store や GoogleのPlayストア を通すしかありませんでした。利用者にとっては安心感がある反面、他の会社が提供するアプリストアを自由に選ぶことはほとんどできず、選択肢が限られていました。その結果、価格や手数料の面で利用者が不利になることもあったのです。こうしたAppleやGoogleのような大手プラットフォームは、アプリ市場の「入り口」を握っていることから、「ゲートキーパー」と呼ばれています。
スマホ新法は、この状態を以下のように改善することを目指しています。
- もっと自由にアプリを選べること
- 料金やサービスが分かりやすくなること
- 安全性がしっかり確保されること
AppleやGoogleの独占にブレーキをかける仕組みの可能性
この法律の大きなポイントは、「ゲートキーパー」と呼ばれる巨大プラットフォーム企業の独占に制限をかけることです。ゲートキーパーとは、スマホ市場においてアプリの入り口をほぼ支配している存在のことで、AppleやGoogleが典型的な例です。
つまり、スマホ新法は「AppleやGoogleが自分のルールだけでアプリ市場をコントロールできないようにする」ためのブレーキ役。これにより、利用者にとって選択肢が増え、サービスの競争が進むと期待されています。
スマホ新法はいつから施行?(2025年12月18日全面施行)
日本での施行時期
スマホ新法は2024年に成立し、公正取引委員会が2025年7月29日に発表した政令とガイドラインによって、12月18日に全面施行されることが正式に確定しました。
今後、アプリの配信や課金ルールなどに大きな変化が訪れるのは、このタイミングからです。
スマホ新法の成立から全面施行までの主要なスケジュールを整理しました。
| 年月 | 出来事 |
|---|---|
| 2024年 | スマホ新法が国会で成立 |
| 2025年3月31日 | 特定ソフトウェア事業者(Apple・Google)を公正取引委員会が指定 |
| 2025年7月29日 | 政令・ガイドライン公表 |
| 2025年12月18日 | 全面施行 |
公正取引委員会による監督
この法律を実際に運用・監督するのは、公正取引委員会です。公取委は、AppleやGoogleのような「ゲートキーパー企業」が不公正な取引を行っていないかをチェックし、必要に応じて改善を求める権限を持っています。違反があれば勧告や命令を出し、最終的には罰則も科せられる仕組みです。
施行日は公正取引委員会の2025年7月29日公表で「令和7年12月18日」と明記されています。あわせて、2025年3月31日の公表でApple・Google等の特定ソフトウェア事業者の指定も告知されています。
さらに詳細な内容は (令和7年3月31日)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律における特定ソフトウェア事業者の指定について をご確認ください。
スポンサーリンク
スマホ新法で何が変わる?
スマホ新法によって、私たちのスマホ利用にはどんな変化があるのでしょうか。特に注目されているのは AppleのApp StoreやGoogle Playストアのルール変更、端末販売の値引き制限、そしてサポートサービスや機能制限の見直し です。ここでは、スマホ新法で具体的に変わる点を整理します。
アプリストアのルール変更(Apple・Googleへの影響)
これまでアプリを購入したり課金したりする際、AppleのApp Store と GoogleのPlayストア が必ず通る仕組みになっていました。その際に発生するのが、いわゆる 「Apple税(30%問題)」 と呼ばれる手数料です。スマホ新法では、こうした手数料や課金方法のルールが見直され、外部決済や代替の課金ルートが認められる可能性があります。
これにより、アプリ開発者がユーザーに直接課金を案内できるようになり、利用者にとって価格が下がる可能性も出てきます。また、App StoreやPlayストア以外の代替アプリストアが登場する余地も広がります。こうしたルール変更は、公正取引委員会が独占禁止法の観点から監督することになり、AppleやGoogleの市場支配を抑える狙いも含まれています。
端末販売・料金の透明化
スマホの本体代金と通信契約がセットになって分かりにくい、という課題もありました。スマホ新法では、値引きの上限を設定したり、通信契約と端末販売を分離したりする仕組みが導入されます。これにより、「実際にいくら払っているのか」が明確になり、消費者が契約を比較しやすくなることが期待されています。
サポートサービスや機能制限の変化
法律でルールが変わると、事業者側が新しい対応策を取ることもあります。実際にEUで施行された デジタル市場法(DMA) では、Appleが一部の機能をEU地域でだけ制限する動きを見せました。たとえば、MacからiPhoneを操作する一部の便利な機能をEU限定で使えなくする、といった対応です。
日本でも同じように、利用者が受けられるサポートサービスや機能の提供範囲が変わる可能性があり、注目されています。
スマホ新法のメリット
スマホ新法が施行されることで、利用者にとって次のようなメリットが期待できます。
アプリ価格が下がる可能性
これまでアプリやアプリ内課金は、AppleのApp StoreやGoogle Playストアを通す仕組みになっており、30%前後の手数料が上乗せされるのが一般的でした。新しい法律では、外部決済や代替アプリストアの利用が広がることで、手数料が下がり、アプリの価格やサービス料金が安くなる可能性があります。
利用者の選択肢が増える可能性
スマホ新法の目的の一つは、利用者により多くの選択肢を提供することです。AppleやGoogleのストアだけでなく、他の会社が提供するアプリストアや課金方法が利用できるようになれば以下の可能性があります。
- 価格で比較して選べる
- 利便性に合わせてサービスを選べる
という自由度が高まり、結果として、市場全体の競争が活性化し、より便利でお得なサービスが登場すると期待されます。
スマホ新法のデメリット
スマホ新法にはメリットがある一方で、注意しておきたいデメリットも存在します。
セキュリティリスク(ウイルス・マルウェア)
これまでAppleやGoogleの公式ストアを通じて配布されるアプリは、厳しい審査を受けていました。そのため、ウイルスやマルウェアに感染するリスクは比較的低く抑えられていました。
しかし、スマホ新法によって代替アプリストアや外部決済が広がると、利用者自身が安全性を判断する機会が増えるため、セキュリティリスクが高まる可能性があります。これは独占禁止法の観点で市場を自由化するメリットの裏返しとも言えます。
セキュリティ対策のポイント
- アプリは信頼できる配信元から入手する
- インストール時の権限要求を確認する
- セキュリティアプリを活用する
サポートの弱体化の懸念
AppleやGoogleのストアを通して購入したアプリは、トラブルが起きても一定のサポートが受けられました。
しかし今後は、外部ストアや別の課金ルートを使った場合、「誰に問い合わせればいいのか分からない」という状況が生じる可能性があります。結果として、従来よりもサポート体制が弱まる懸念があります。
ITリテラシーが必要になる
これまでのように「公式ストアを使えば安全」というシンプルな構造ではなくなるため、利用者のITリテラシー(情報を正しく理解し、安全に使う力)がこれまで以上に求められます。
安全性を意識せずにアプリを選ぶと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあり、利用者自身が注意して判断することが大切になります。
スポンサーリンク
EUのデジタル市場法(DMA)との比較
スマホ新法は日本独自の法律ですが、その背景には EUで先行して施行された 「デジタル市場法(DMA、EUデジタル市場法)」 の存在があります。DMAは AppleやGoogleといったゲートキーパーを規制するための法律 で、日本のスマホ新法もこの流れを参考にしています。ここでは、DMAのポイントと日本の独占禁止法との違いを整理します。
EUでのゲートキーパー規制(DMAのポイント)
EUのDMAでは、欧州委員会がAppleやGoogleを「ゲートキーパー企業」と公式に指定し、以下のような規制を課しています。
- アプリストア以外の課金や配布ルートを認めること
- 自社サービスを優遇しないこと
- デフォルト設定の自由化(ブラウザや検索エンジンを選べるようにする)
この結果、AppleやGoogleはビジネスモデルの見直しを余儀なくされました。
Appleの機能制限(EU限定機能廃止の例)
DMAの影響を受け、AppleはEU域内で一部の機能を制限しました。代表例として、
- MacからiPhoneを操作する便利な機能(サイドローディングや連携機能)をEUでは停止
- 安全性やセキュリティを理由に、一部の開発者向け機能をEUでのみ利用不可に設定
Appleは「セキュリティ確保のため」と説明していますが、法律に対する強い姿勢を示すための戦略的対応とも受け止められています。
👉 AppleはDMA対応として iOS / Safari / App Storeの変更を公式に公表 しており、詳細は公式発表ページで確認できます。
日本の独占禁止法との違い
日本のスマホ新法はEUのDMAに影響を受けていますが、位置付けはやや異なります。
- EU:ゲートキーパーを直接規制する包括的な法律
- 日本:既存の 独占禁止法を補完する形 で制定され、監督は公正取引委員会が担当
つまり、日本では「スマホ市場に特化した独禁法の特別法」という位置付けです。DMAほど包括的ではありませんが、AppleやGoogleの独占的な慣行に歯止めをかける狙いは共通しています。
本記事の内容は、公正取引委員会や経済産業省が公開している資料、ならびにEU欧州委員会の公式発表を参考に一般向けに解説しています。
詳細は以下の公式ページをご確認ください。
・公正取引委員会 公式サイト
・経済産業省 公式サイト
・EU欧州委員会 デジタル市場法(DMA)ページ
スポンサーリンク
AppleとGoogleはどう対応する?
スマホ新法の施行によって、AppleとGoogleの対応は注目されています。両社は「ゲートキーパー」として指定される可能性が高く、今後の動きが利用者に直結します。
| 企業 | 従来の対応 | 新法への対応見込み |
|---|---|---|
| Apple | 外部課金を認めず、App Storeを独占。アプリ内課金に最大30%の手数料を課してきた。 | 外部課金や代替ストアを限定的に解放する可能性。ただし「セキュリティ保護」を理由に機能制限を設ける可能性あり。 |
| Androidでは外部ストア利用は可能だが、事実上Playストアが標準。手数料回避は難しかった。 | 外部決済や代替ストアをさらに広げ、競合事業者が参入しやすくなると見込まれる。 |
Appleのスマホ新法対応:外部課金・代替ストア
Appleはこれまで、App Storeを通さない外部課金を認めない姿勢をとり、アプリ内課金に最大30%の手数料を課してきました。しかし、スマホ新法の施行後は、外部課金を認める方向に調整する可能性があります。また、EUのDMA対応と同様に、代替アプリストアを限定的に解放する措置を取ることも想定されます。
ただし、Appleは一貫して「セキュリティとユーザー保護」を理由に規制緩和に慎重であり、日本でもEUと同じように一部機能の制限を設ける可能性が指摘されています。
こうしたAppleの対応は、日本のiPhoneユーザーにとって アプリの価格や利用可能な機能の変化に直結するため、大きな注目を集めています。
Googleのスマホ新法対応:Playストアの開放と競合への影響
GoogleはすでにAndroidの仕組み上、Appleよりは柔軟に外部ストアを許可しています。それでも、これまではPlayストアが事実上の標準となっており、開発者はGoogleの手数料を避けにくい状況でした。
スマホ新法の影響で、Googleは外部決済や代替ストアの利用をさらに広げる必要が出てきます。これにより、国内外の事業者が独自のアプリ配信サービスを展開しやすくなり、競合の参入が加速する可能性があります。
独占禁止法の観点から見た今後
スマホ新法は、既存の独占禁止法を補完する特別法として位置付けられています。公正取引委員会は、AppleやGoogleが自社の優遇や不公正な取引を続けていないかを監視し、必要に応じて勧告や命令を行います。
今後は、両社の対応次第で「市場競争が活性化し、利用者の利便性が高まる」のか、それとも「機能制限などで利便性が損なわれる」のかが分かれると考えられます。
まとめ|スマホ新法で知っておくべきこと
スマホ新法は、2025年12月18日に全面施行される予定です。ここまでの内容を踏まえ、施行時期やメリット・デメリット、AppleやGoogleへの影響を整理し、スマホ新法で知っておくべきことを簡単にまとめます。
スマホ新法の施行時期と基本ポイント
- 施行日:2025年12月18日
- 監督:公正取引委員会(独占禁止法を補完する特別法の位置付け)
- 対象:AppleやGoogleのアプリストアや課金ルールなど
スマホ新法のメリット・デメリットまとめ
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| アプリ価格 | 手数料減で安くなる可能性 | 外部決済は安全性確認が必要 |
| 選択肢 | 代替ストア登場で選べる幅が広がる | サポート窓口が分散する懸念 |
| 利便性 | 市場競争が活性化しサービス向上 | ITリテラシーが求められる |
iPhone・Appleユーザーが注意すべきポイント
- EUの事例のように、一部の便利な機能が制限される可能性がある
- 外部課金や代替ストアの導入により、料金が下がる一方で安全性の確認が自己責任になる
- iPhoneユーザーは特に、今後のAppleの対応に注意する必要がある
スポンサーリンク
よくある質問(FAQ)
スマホ新法はいつから施行されますか?
スマホ新法は 2025年12月18日 に全面施行されます。公正取引委員会が監督し、AppleやGoogleのような「ゲートキーパー」企業に新しいルールが適用されます。
スマホ新法でアプリ課金は安くなりますか?
スマホ新法の施行により、外部課金や代替アプリストアの利用が広がる可能性があります。その結果、Appleの「30%問題」に代表される高額な手数料が下がり、アプリ課金が安くなる可能性があります。ただし、すべてのアプリが値下げされるわけではなく、開発者や事業者の判断によって変わります。
iPhoneで使えなくなる機能はありますか?
EUのデジタル市場法(DMA)対応では、Appleが一部の機能(MacとiPhoneの連携機能など)をEU限定で制限しました。日本でも同様に、iPhoneで一部機能が制限される可能性が指摘されています。ただし、具体的にどの機能が対象になるかはまだ明らかにされていません。
スマホ新法でセキュリティは大丈夫ですか?
スマホ新法によって、App StoreやGoogle Playストア以外のルートからアプリを入れる機会が増えるため、セキュリティリスク(ウイルス・マルウェア)が高まる可能性があります。
安全に使うためには、以下のような対策が重要です。
- 信頼できるストアや配信元からのみアプリを入れる
- インストール時に要求される権限を確認する
- 必要に応じてセキュリティアプリを導入する
※本記事は、公正取引委員会・経済産業省の公開資料および EU欧州委員会の公式発表をもとに一般向けに解説したものです。法律的な助言や公式見解を示すものではありません。最新かつ正確な情報は、必ず各公式サイトをご確認ください。
参考:
スポンサーリンク